この記事を読んでわかること
- 「ぼたん」の行き方
- 「ぼたん」の店内の様子
- 「ぼたん」の料理について
「ぼたん」の行き方
最寄り駅が多い
お店のホームページでは以下のアクセスの案内があります。
地下鉄丸の内線 淡路町駅 銀座方面A3番出口(徒歩2分)
公式サイトより
地下鉄丸の内線 淡路町駅 池袋方面A5番出口(徒歩3分)
都営新宿線 小川町駅 A3番出口(徒歩2分)
地下鉄銀座線 神田駅 6番出口(徒歩5分)
JR 神田駅 東口(徒歩7分)
JR 秋葉原駅 電気街口(徒歩7分)
JR 御茶ノ水駅 聖橋口(徒歩8分)
電柱に注目
先に書いた通り最寄り駅は多いのですが、この辺りは細かい道が多く地図を見てもわかりにくいかもしれません。
お店の近くに電柱に「2つ目の角を右」のような案内があるのでそれを頼りに行くと迷子にならないと思います。
しかし、問題もあります。読めない字で書いてあるのです。
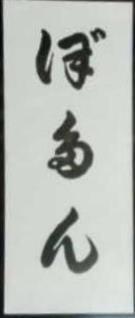
昭和4年に建てられ東京都の歴史的建造物になっています。

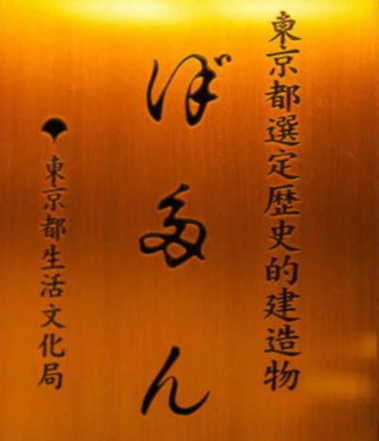
創業は明治30年。関東大震災のときに被災し現在の建物は昭和4年に建てられ東京都の歴史的建造物に選定されています。
この界隈は昭和20年の空襲でも被害が少なかった地域です。
「ぼたん」の店内の様子
下足番の人に札をもらいます
暖簾をくぐり店内に入ると下足番の人が札をくれますので靴を脱いだまま上がります。
予約名を告げると女中さんが部屋まで案内してくれます。階段が急なので膝が悪い人は1階の個室の予約をおススメします。
「階段は登れるけどあぐらがかげない」「正座ができない」人は事前にお店に伝えると正座椅子を用意してくれるみたいです。


西郷隆盛の書

「人生」しか読めんな。とかみんなで言ってましたが。正しくは「敬天愛人(けいてん-あいじん)」でした。
「敬天」は天をおそれ敬うこと。 「愛人」は人をいつくしみ愛すること。らしいです。
「西郷どん」が常連だったのかな?と考えましたが、お店は創業明治30年で、西郷隆盛は明治10年没なので違いました。
「ぼたん」の料理について
小さいテーブル

座った前には小さいテーブルがありました。
「こんな小さなテーブルで鍋が食べられるのか?」と疑問に思いつつ先付けのマグロの角煮を頂きました。
しっかり味がついて美味しかったです。
鍋と食材の登場
きれいなタマゴ


ちびちび飲んでいたら卵が配膳されました。
きれいなタマゴです。期待が高まります。
鍋と炭火が登場

燃え盛るこだわりの備長炭の上に鉄鍋が置かれました。
普通の旅館の一人鍋の固形燃料とは火力が違います。
初めに部屋に入る前に廊下にあったのを気づいていましたが写真を撮るのを忘れていました。
具材登場


毎朝捌く新鮮丸鶏
こちらのお店は毎朝丸鶏を捌くそうです。種類は「ムネ」「モモ」「ささみ」「モツ類」です。つくねは親鳥とのことでした。
余談ですが、「つくね」と「つみれ」はトリと魚などの材料の違いではなく「成形してあるものはつくね」「直前に成形する(摘む)物はつみれ」らしいです。
「ぼたん」専用の白滝と豆腐
白滝と豆腐はお店の味付けに合うように専用に作っているとのことでした。
最初は仲居さんが作ってくれます
鍋が十分熱したころに仲居さんが鶏の油を鍋に引き具材と割り下を入れてくれます。そのあとは自分たちで鍋を育てます。

炭火なので火力の調整はできません。火力が強いのでにすぎないように食べる分だけ入れていきます。
お肉は弾力がありますが柔らかいです。細めのちぢれた白滝も汁を吸って美味しいです。変わった形の豆腐も美味しいです。
卵は1人前が2個です。3個食べたいときは150円で追加できます。
〆の卵とじ(親子丼)
シメに残った具材で親子丼が食べられます。なので具材は残しておく必要があります。(追加料金でお替りもできます)

御新香と水菓子



お腹いっぱいになりました。ごちそうさまでした。
今回紹介したお店
最後までお読みいただきありがとうございました。
【広告】
コーヒー・紅茶・お茶の人気店のこだわりの味をおうちで楽しめる。
【キューリグオンラインストア】